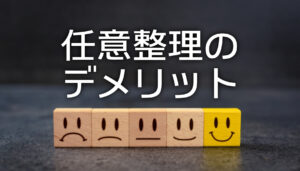「任意整理って、結局いくらかかるの?」そう感じて検索された方は多いはずです。
まずお伝えしたいのは、任意整理の費用は「1社あたりいくら」で計算されるのが基本だということ。借入先が複数ある場合、費用もそのぶん加算されますが、相談先や手続きの進め方次第で抑えることも可能です。
ここでは、任意整理にかかる代表的な費用の内訳と相場感について、わかりやすく整理していきます。
任意整理の費用は大きく3つに分かれる
| 費用項目 | 説明 | 相場(1社あたり) |
|---|---|---|
| 着手金 | 手続き開始時に必要な費用 | 2〜5万円程度 |
| 報酬金 | 和解成立後に発生する費用 | 2〜5万円程度 |
| 減額報酬 | 減額できた金額の◯%として発生 | 減額額の10%程度が相場 |
| 実費 | 郵送費や交通費など | 数千円〜1万円未満 |
仮に「3社から借入があり、合計で150万円」だとすると、着手金+報酬金で約15〜30万円程度。
さらに減額報酬が加わると、総額で20万〜40万円前後になることが多いです。
料金体系は事務所ごとに異なる
任意整理の費用は「全国共通の公定価格」があるわけではありません。
事務所によって、
- 着手金0円(報酬で回収)
- 減額報酬なし(定額制)
- すべて込みで◯万円というパック料金
など、独自の料金体系を採用しているケースもあります。
 金崎
金崎弁護士・司法書士のどちらに依頼するかによっても、料金感は異なるため、次章でそれぞれの違いについて詳しく見てみましょう
弁護士と司法書士の費用比較|依頼先でどう違う?
「弁護士に頼むと高そうだから、司法書士のほうが安いのでは?」
任意整理を検討している方の中には、そんな疑問を抱く人も多いでしょう。
結論からお伝えすると、費用の差はありますが、“安ければ良い”という単純な比較ではありません。
ここでは、任意整理における「弁護士と司法書士の違い」について、費用・対応範囲・得意分野など、複数の視点から比較していきます。
弁護士と司法書士の主な違い
| 比較項目 | 弁護士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 対応できる借金額 | 制限なし | 1社あたり140万円以下 |
| 着手金の相場 | 3〜5万円/社 | 2〜4万円/社 |
| 減額報酬の相場 | 10%前後 | 同等か少し低め |
| 訴訟対応 | 可能 | 原則不可(簡裁代理権があれば可能) |
| 債権者との交渉力 | 高い傾向 | 事務所により差あり |
「安さ」だけで選ばないほうがいい理由
司法書士のほうが費用がやや安い傾向にありますが、すべての人に適しているとは限りません。
例えば
- 借金額が大きく、1社あたりの債務が140万円を超える場合 → 弁護士にしか対応できません。
- 債権者側が訴訟をちらつかせてくる場合 → 弁護士でなければ対応不可なケースもあります。
つまり、「どちらがいいか」はあなたの借金状況や交渉難易度によって変わるのです。



費用だけ見れば司法書士のほうが安く感じる…



たしかに。でも、対応できる範囲に制限があるんだ。借金が多い人や、交渉が難航しそうな場合は弁護士のほうが安心だよ
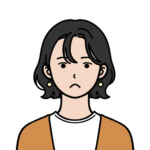
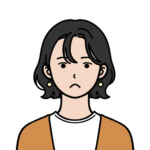
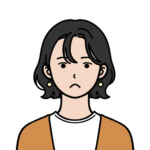
そっか、単純に安さだけで決めちゃうのは危ないですね



うん。費用感は大事だけど、それ以上にその人に合った対応をしてくれるかがポイントなんだ
任意整理の費用を抑える方法と注意点
「任意整理をしたいけど、費用が高そうで踏み出せない…」
そんな気持ちから、相談をためらっている方も少なくありません。
ですが、ご安心ください。任意整理は「お金に困っている人のための制度」だからこそ、費用面の配慮も数多く用意されているのです。ここでは、費用をできるだけ抑えて任意整理を進めるための具体的な工夫と、その際に気をつけるべきポイントを整理していきます。
よくある費用を抑える工夫(4選)
① 分割払いの相談を活用する
ほとんどの法律事務所では、着手金や報酬金を「分割で支払う」ことが可能です。
たとえば、1社につき3万円の費用がかかる場合でも、月々5,000円〜10,000円の分割に応じてくれることがあります。
② 減額報酬なし or 一律料金の事務所を選ぶ
最近は、「減額報酬ゼロ」や「定額制のパック料金」を打ち出している事務所もあります。
費用が明朗で、あとから追加費用が発生しない点が安心です。
③ 初回無料相談で複数事務所を比較
1社目で即決するよりも、複数の事務所で無料相談を受け、料金体系を比較することで、自分に合ったところが見つかりやすくなります。
④ 法テラス(民事法律扶助制度)を検討する
収入や資産が一定基準以下であれば、法テラスを通じて弁護士費用を立て替えてもらうことができます。
分割での返済も可能なので、まとまったお金がなくても手続きが進められます。
注意すべき点|“安さ”だけを基準にしない
「安さ」を優先しすぎると、以下のようなリスクもあります。
例えば
- 経験や実績が少ない事務所だと、交渉で不利になる可能性がある
- 「着手金0円」の裏で、報酬金が高額に設定されているケースもある
- 追加費用(訴訟対応・辞任時の精算など)の説明が曖昧なことも
大切なのは、“総額でいくらになるのか”と、“トラブル時の対応”まで含めて比較すること。



取り立てに焦って依頼しようとすると、つい“着手金0円”に飛びついちゃうかも…



その気持ち、すごく分かる。でも0円の裏にある契約条件や追加費用を見逃すと、結果的に高くついてしまった、ということもあるんだ



費用は分割できるかや説明が明確かもポイントですね



信頼できる事務所かどうかは、「安さ」だけでなく「誠実さ」もしっかり見極めよう
任意整理の費用を支払えない場合の対処法
「任意整理をしたい気持ちはあるけれど、費用を用意できそうにない…」
そんな悩みを抱えて検索にたどり着く方は、実際とても多いのです。
ですが、安心してください。「お金がないから任意整理できない」ということはありません。
ここでは、どうしても費用が払えない場合でも、無理なく相談・手続きを進めるための選択肢をご紹介します。
法テラス(日本司法支援センター)の活用
- どんな制度?
-
法テラスは、経済的に余裕のない方に対して、弁護士費用などを一時立て替えてくれる公的な制度です。
- 条件はある?
-
はい。以下のような収入と資産の基準をクリアする必要があります。
- 単身者の場合:収入月額20万円以下(地域差あり)
- 預貯金などの資産:原則180万円以下
- 借金の理由がギャンブルや浪費でないこと など
- どんなサポートが受けられる?
-
- 弁護士費用や実費の立て替え
- 月々5,000〜10,000円程度での分割返済
- 対応弁護士の紹介も可能
「いきなり自己資金で数十万円」という負担がなくなるため、費用がネックで踏み出せなかった方にとって非常に心強い制度です。
分割払いの交渉をする
法テラス以外でも、多くの事務所が分割払いに対応しています。
例えば
- 3万円の着手金を6回払い(月々5,000円)
- 手続き完了後の報酬金も、3ヶ月〜1年かけて分割可能
「まとまったお金がないから無理…」と諦めずに、まずは「分割にできますか?」と相談してみることが大切です。
状況によっては、他の債務整理も視野に
もし法テラスの利用も難しく、返済の見込みが立たない場合には、「個人再生」や「自己破産」など、他の手続きが適している可能性もあります。
任意整理は「将来利息のカット」や「返済負担の軽減」が主な効果なので、元本が多すぎる場合は、根本的に減額できる手続きを検討すべきです。



「お金がないから相談できない」って、実は思い込みだったんですね…



うん。お金の悩みこそ、専門家に頼っていいんだよ。法テラスも分割払いも、ちゃんと使えば強い味方になる



知らないでいると、もったいないかも



問題を先送りせず、無料で相談して情報を集めていこう
任意整理の費用に関するよくある質問と回答
「費用がどれくらいかかるかは分かったけど…」
実際に手続きを検討し始めると、もっと細かい疑問が出てくるものです。
ここでは、任意整理の費用について、よくある質問をQ&A形式でまとめました。
不安や誤解を一つひとつ丁寧にクリアにしていきます。



減額報酬って、元金にかかるのかと思ってました…



その勘違い、よくあるんだ。正確には利息や遅延損害金のカット額に対してだよ



細かいところまでちゃんと説明してくれる事務所を選びたいですね



そうだね。金額だけじゃなく、説明力と透明性も判断基準にしてほしいな
任意整理の費用は「事前に知れば怖くない」
任意整理にかかる費用は、一律ではありません。
事務所によって料金体系は異なり、減額報酬の有無、着手金の分割対応、法テラスの利用可否など、細かな違いがあります。
だからこそ「知らなかった」「思ったより高かった」。
そんな事態を防ぐためにも、この記事で得た知識をもとに、“納得できる相談先”を見つけることが何より大切です。
費用に不安があっても、分割払いもあれば、立て替え制度もある。
つまり、相談できない理由は、ひとつずつ減らせるんです。
早めに信頼できる専門家に相談することが、未来の自分にとって、最良の選択になります。