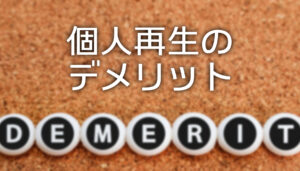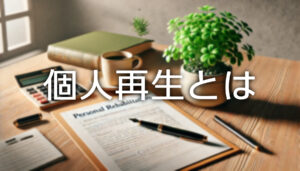まずは全体像を知ることから
「個人再生って、裁判所の手続きがあるから難しそう…」
「自宅を守れるって聞いたけど、実際はどう動けばいいの?」
そう思って検索された方も多いのではないでしょうか。
個人再生は、借金の大幅減額と再スタートを実現できる制度ですが、全体の流れが見えないと“そもそも自分にできるのか”という不安が先に立ってしまうのが現実です。
 金崎
金崎この記事では、個人再生を検討している方が「何から始めて、どう進んで、どう終わるのか」を、6つのステップに分けて整理していきます
個人再生の流れは6つの段階|完了までの全体像を押さえよう
個人再生は、裁判所を通じて借金の減額を図り、原則3〜5年で再建を目指す法的手続きです。
「難しそう」「時間がかかりそう」という印象を持つ方が多いですが、実際の流れを把握しておけば、落ち着いて進めることができます。
ここでは、弁護士や司法書士に依頼した場合をベースに、個人再生の6ステップを時系列で紹介します。
個人再生の基本的な流れ【一覧】
まずは、借金問題に強い法律事務所に相談しましょう。
初回は無料相談を設けている事務所も多く、収入状況や債務額をヒアリングしてもらえます。



内容に問題がなければ、正式に受任契約を結び、ここから手続きがスタートします。
受任後、債権者(借入先)に対して「受任通知」を発送。
これにより、債権者からの督促や返済請求は法律的に一時ストップします。
このタイミングが、多くの方にとって「精神的にホッとする瞬間」となるでしょう。
受任通知と並行して、以下のような申立書類の準備を進めます。
- 債権者一覧表
- 給与明細・源泉徴収票
- 家計簿や収支表
- 財産目録(不動産・車など)
これらを弁護士が整理し、裁判所へ個人再生の申立てを行います。
申立後、月々の返済予定額を試しに支払う「履行テスト」が始まります。
これは、将来の返済能力があるかどうかを示すための“テスト支払い”です。



あわせて、債務額・返済期間・財産の状況を元に「再生計画案(返済スケジュール)」を作成し、裁判所に提出します
小規模個人再生の場合は、債権者による「不同意」がなければ、手続きが進みます。
一部の地裁では「再生委員(弁護士)」が選任され、再生計画の妥当性や支払い能力の確認が行われます。
※この再生委員がつくかどうかで、期間や費用が増減します。
再生計画案が認可されると、「開始決定」が下され、返済がスタートします。
計画に沿って3〜5年かけて減額後の借金を返済していくのが、個人再生の最終ステップです。
この間、収入状況や家計を安定させることが大切です。
個人再生はどれくらいの期間で完了する?
平均的な期間は約6〜10ヶ月
個人再生の申立てから認可決定までにかかる期間は、6〜10ヶ月程度が一般的です。
- 受任〜申立て準備:約1〜2ヶ月
- 申立て〜再生計画案の提出:約2〜3ヶ月
- 債権者確認・裁判所認可:約3〜5ヶ月
※住宅ローン特則の有無や、裁判所の対応状況によって変動します。
裁判所や債権者の対応で長引くこともある
再生委員がつく地域や、債権者が多数いる場合、手続きは長期化しやすくなります。
また、申立書類の不備・家計管理の不明瞭さなども遅延の原因に。



個人再生って半年〜1年くらいかかるんですね…意外と長い!



でもその分、借金を5分の1とかに減らせる可能性があるんだ



家を残したまま、そんなに減らせるなら…たしかにその時間は投資かも



そうだね。準備と覚悟がある人ほど、きちんと再生できる制度なんだよ
個人再生の流れで気をつけたい落とし穴と注意点
手続きの流れが分かったからといって、安心するのはまだ早いかもしれません。
個人再生は、裁判所が関与する法的手続きである以上、想定外の落とし穴に引っかかって途中で止まってしまうケースも少なくありません。
ここでは、手続き中によくある「つまずきポイント」と「未然に防ぐための知識」を整理します。
履行テストでつまずくと認可が下りないこともある
履行テストとは「試し返済」のこと
個人再生における履行テストとは、提出予定の返済計画案どおりに数ヶ月間(一般的には、3〜6ヵ月)、試しに返済を行う手続きです。
例えば
月2万円ずつ返済する計画なら、
その金額をあらかじめ指定口座に入金していきます。
この履行テストに通らないと、裁判所は「返済能力に疑いあり」と判断し、再生計画の認可を却下する可能性もあるため、非常に重要なステップです。
入金忘れや無計画な支出に注意
「うっかり忘れた」「他の支払いに回してしまった」
これらの理由で履行テストに失敗し、申立を取り下げざるを得なくなる人もいます。
失敗例
- 給料日と入金日をあらかじめ調整しておく
- 生活費と返済資金を分けて管理する
- 家計簿アプリや自動振込などを活用する



といった形で、「確実に、絶対に入金を継続できる仕組み」を整えることが欠かせません。
住宅ローン特則の手続きは通常より複雑
自宅を残す場合はローン返済と並行して行う必要がある
住宅ローン特則を使うと、家を手放さずに個人再生が可能になります。
ただしこの場合、通常の再生手続きに加えて、以下のような条件をクリアする必要があります。
住宅ローン特則の条件
- ローンの支払いを今後も継続できること
- 担保権者(金融機関)が認める返済条件を守ること
- 住宅ローンの残債が返済計画に影響しないよう配慮
つまり、「家を守りたい」という気持ちと、「他の借金を再生する」という2つの軸を、きちんと両立させなければならないというわけです。
手続き書類・条件が厳しく、専門家の助力が必須
住宅ローン特則の利用には、以下のような書類・条件が必要です。
必要書類・条件
- 登記事項証明書(不動産の権利関係)
- 住宅ローン返済表・契約書
- 住宅資金特別条項に関する詳細記載



提出書類の種類も多く、記載内容も複雑なため、専門家(弁護士)の関与はほぼ必須みたいです
再生委員がつくかどうかで進行・費用が変わる
地裁によっては再生委員の選任が必須
地方裁判所によっては、個人再生申立時に「再生委員(通常は弁護士)」が選ばれるケースがあります。
再生委員の役割
- 申立人の収入・生活状況の調査
- 再生計画案の妥当性チェック
- 裁判所への報告書提出
などを担います。
東京地裁・横浜地裁などは原則再生委員付きで進行するのが通例です。
再生委員がいると報酬・報告義務が増える
再生委員が選任されると、以下のような影響があります。
- 報酬相場:約15〜25万円(予納金とは別途)
- 追加の面談や資料提出の負担
- スケジュールの柔軟性が下がる
「費用を抑えて進めたい」「極力対面せずに済ませたい」と考えている方は、“再生委員がつく地裁かどうか”を事前に確認しておくことが重要です。



履行テストって、ただの形式かと思ってたけど…リアルに審査されるんですね



うん。「この人は3年払い続けられるか」を裁判所が見る、すごく大事なテストだよ
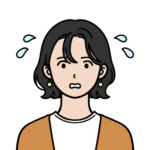
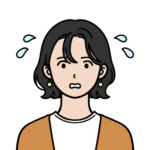
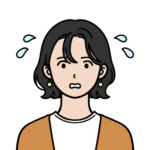
住宅ローン特則も、便利だけどハードルは高そう…



家を守るってことは、それだけ準備も必要になるね
個人再生手続きの前に準備すべき3つのこと
「いざ申し立てよう!」と思っても、何の準備もなくスタートするのは危険です。
裁判所に提出する書類の多さ、収支バランスのチェック、家族への配慮などなど。
スムーズな個人再生を進めるためには、手続き前の準備が“成否”を分けるといっても過言ではありません。
ここでは、「いますぐやっておくと安心な3つの準備」を整理しました。
毎月返済できる安定した収入の確認
給与明細や家計の収支表を準備
個人再生を使うには「将来的に継続して返済できること」が前提です。
そのため、以下のような収入証明書類を用意しておきましょう。
- 直近2〜3ヶ月の給与明細
- 源泉徴収票(または確定申告書)
- 家計簿(収入・支出のバランスが分かるもの)
- 雇用契約書(パート・アルバイトの方は特に)
この情報をもとに、「履行テスト」や「再生計画案」の返済額が設計されていきます。
副業・手当収入も含めて報告する
収入には「給与」だけでなく、
- 配偶者の収入
- 子ども手当
- 副業や不定期な収入
- 年金・障害年金
なども含まれます。



こうした収入源も、しっかり記載・報告しておくことで、返済可能性の裏付けになります
必要書類は早めにチェックして揃えておく
給与明細・住民票・ローン契約書・課税証明書など
申立に必要な書類は多岐にわたります。
代表的なものは以下のとおりです。
| 書類名 | 発行元・取得方法 |
|---|---|
| 住民票 | 市区町村役場で取得(発行日から3ヶ月以内) |
| 給与明細 | 勤務先から入手 |
| 課税証明書 | 市区町村役場で取得 |
| 財産目録 | 自己作成(保険・不動産・車など) |
| 債権者一覧表 | 借入先の情報一覧(事務所が作成補助) |
| 各種ローン契約書 | 借入当時の契約書や返済明細 |
役所・勤務先に発行依頼が必要なものは早めに動く
とくに、「課税証明書」「住民票」「保険契約書類」などは、手配に数日〜1週間程度かかることも。
申し立てを急ぐ場合は、書類の確認と取り寄せを最優先タスクにするのがベストです。
申立費用・弁護士費用の準備も計画的に
裁判所への予納金は2〜3万円程度が相場
個人再生では、裁判所へ「予納金」を支払う必要があります。
予納金とは、事務処理や郵送費などに充てられる費用で、相場は以下のとおりです。
予納金の相場
- 再生委員なしの地裁:2〜3万円
- 再生委員ありの地裁:15〜25万円(再生委員報酬込み)
この金額は一括で支払う必要があるため、事前に確認しておきましょう。
弁護士費用は分割払いに対応している事務所もある
弁護士への報酬相場は30〜50万円前後ですが、
最近では、「受任後の分割払い」「法テラスの費用立替」などを導入している事務所も増えています。
- 初期費用ゼロ(着手金無料)
- 相談料・見積もり無料
- 月1〜3万円での分割払い対応
などの条件を比較し、自分に合った支払い方法を選ぶことが大切です。



申し立て前の準備だけで、けっこうやることあるんですね…!



そうだね。逆に言えば、これをやっておけば安心して進められるっていう目安でもあるよ



事前準備で失敗を防げるんですね



制度を使いこなすには、焦らず、一歩ずつ行こう
個人再生の流れを知ったら|よくある疑問を解消しよう
この章では、個人再生に関するよくある不安・疑問を、制度の裏側も踏まえて一つずつクリアにしていきます。
手続き中に家族や会社に知られることはある?
郵送物・書類名義の配慮で防げるケースが多い
まず、多くの人が不安に思うのが「バレるリスク」です。
特に、以下のような点が気になります。
- 書類が自宅に届いて同居家族にバレるのでは?
- 勤務先に何らかの連絡が行くのでは?
しかし実際には、多くの法律事務所で「配慮した対応」が可能です。
こんな対応も可
- 郵送物の差出人名を事務員名義に変更
- 勤務先への連絡は一切なし
- 郵便物の送付先を別住所に設定可能(実家など)
- LINE・メールでの完全オンライン進行も可能
つまり、希望を伝えておけば、バレるリスクはかなり低く抑えられるのです。
裁判所からの通知も、事務所を通じて対策できる
個人再生は裁判所を通じた手続きですが、直接本人宛に書類が届くとは限りません。
多くの場合、書類のやり取りはすべて弁護士経由で行われるため、家庭に裁判所名の封筒が届くような心配もありません。
ただし、これらの対応は「事前に希望を伝えておくこと」が大前提です。
個人再生の流れを途中でやめることはできる?
申立て前なら中断可能、申立て後は取り下げ申請が必要
「手続きを進めていたけど、やっぱりやめたい」というケースも実際にあります。
この場合、以下のようなステータスによって対応が変わります。
- 申立て前:事務所に中止を伝えれば、すぐストップ可能
- 申立て後(裁判所受理後):正式に「申立て取り下げ書」を提出する必要あり
ただし、受任通知が送られた後に中止すると、債権者との関係がややこしくなる可能性もあるため、中断は早めの判断がポイントです。
手続きを止めると債権者の督促が再開することも
個人再生の準備中に止まってしまうと、再び債権者からの請求や督促が戻ってきます。
特に、任意整理などの代替案を取らないままやめると、
- 督促電話・郵便の再開
- 延滞利息の発生
- 一括請求の可能性
など、リスクが一気に高まるため、中断を決める前に専門家に相談して「次の一手」を整理することが重要です。
個人再生が不認可になるケースとは?
履行テスト不履行・収支のバランス不成立・虚偽申告
個人再生は「申し立てれば必ず認められる」わけではありません。
次のような状況では、裁判所から認可されずに却下されるリスクがあります。
不認可の例
- 履行テストが途中で止まった
- 収入に対して返済額が過剰(=生活維持が難しい)
- 財産や債務の内容に虚偽・申告漏れがある
提出書類のミス・期日遅れも要注意
制度的な問題だけでなく、事務的な不備でも「手続き上の不備による却下」ということがあります。
不備の例
- 提出書類の抜け・誤字脱字
- 記載内容の矛盾(通帳残高と説明のズレなど)
- 裁判所からの連絡を放置
「うっかり」の積み重ねが、重大な結果につながることもあるため、弁護士の指示をしっかり守って進める姿勢が大切です。



人によってはバレるのが怖いとかがあるけど、ちゃんと配慮してくれるんですね



うん、伝えれば柔軟に対応してくれる事務所は多いよ
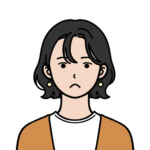
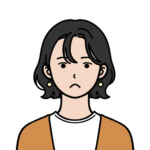
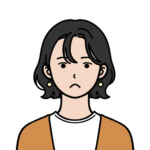
途中でやめるリスクって、想像以上にありそう…



そのあたりは専門家と相談しながら進めたほうがいいね。忘れないように注意しよう
個人再生の流れをスムーズに進めるための専門家の活用法
裁判所とのやり取り、再生計画案の作成、履行テストの管理…。個人再生は、正直に言うと「自分一人ではまず対応しきれない」手続きです。
だからこそ、法律事務所などの専門家に依頼することで、ストレスやリスクを大幅に減らすことが可能になります。
この章では、専門家をどう選び、どう活用すべきかを解説します。
どんな弁護士・司法書士に依頼すればいい?
個人再生の取り扱い実績が豊富な事務所を選ぶ
弁護士・司法書士なら誰でもいい、というわけではありません。
個人再生の取り扱い実績が多く、申立てから認可までの流れを熟知している事務所を選びましょう。
チェックすべきポイント
- 個人再生の解説ページが充実している
- 住宅ローン特則にも対応している
- 自社サイトに申立実績件数を明記
- 再生委員付き地裁にも慣れている
住宅ローン特則に強いかどうかも重要なポイント
「家を守りながら個人再生したい」という方は、住宅ローン特則に詳しい事務所を選ぶことが重要です。
- 実際に住宅ローン特則を含む手続き経験があるか
- 不動産の権利関係や銀行交渉に慣れているか
- 書類対応や交渉の流れを丁寧に教えてくれるか
なども比較ポイントになります。
費用を抑えつつ安心して依頼する方法
分割払い・法テラスの利用も検討できる
「専門家に依頼すると高そう…」と感じる方もいるかもしれませんが、以下のような柔軟な支払い対応をしている事務所も多数あります。
こんな対応も可
- 着手金ゼロ・成功報酬型
- 分割払い(月々1〜3万円)OK
- 法テラス(民事法律扶助制度)の利用が可能
※法テラスは、収入制限などの条件を満たせば、手続き費用を立て替えてもらえる公的制度です。
複数の事務所に相談して比較検討するのもOK
1つの事務所に決めきれない場合は、2〜3件の事務所に相談して比較するのがおすすめです。
- 対応の丁寧さ
- 説明の分かりやすさ
- 手続きの流れの透明性
- メールやLINE対応の有無
これらを比較すれば、「本当に信頼できる事務所」が見えてきます。
2025年の最新動向|オンライン対応や郵送対応の可能性
裁判所によってはWeb会議・郵送申立てに対応中
コロナ禍以降、一部の地方裁判所では以下のようなオンライン対応が広がっています。
- 裁判所との面談をWeb会議で実施
- 書類提出・再生計画案のやり取りを郵送で対応
- 弁護士が“代理出廷”することで本人出廷不要になるケースも
このような対応が可能かどうかは事務所によっても異なるため、最初の相談時に確認しておくと安心です。
非対面での進行を希望する場合は、事前に対応可否を確認
- 裁判所に行くのが不安
- 職場を休めない
- 家族に知られたくない
といった事情がある方は、非対面型のサポート体制が整っている事務所を優先的に検討しましょう。



「再生委員がつくかどうか」とか、「法テラスが使えるか」とか…比べるポイントって意外と多いですね



そうなんだ。手続きだけ進めてくれるだけじゃなくて、どれだけ寄り添ってくれるかも大事だね
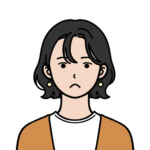
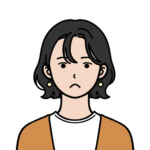
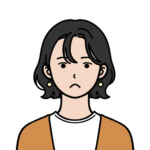
オンライン対応の裁判所があるのも驚きました!



2025年の個人再生は、ずいぶん柔軟になってきてる。情報を知ってる人ほど有利に動ける時代だよ
個人再生の流れを知れば、自分の選択に確信が持てる
ここまで読んでいただいたあなたは、もう流れを掴めたはずです。最後におさらいしておきましょう。
最後に押さえておきたい3つのポイント
- 個人再生は6つの段階で進行し、完了までは6〜10ヶ月程度が目安
- 住宅ローン特則や履行テストなど、“落とし穴”が存在するため事前準備が極めて重要
- 専門家を活用すれば、バレずにスムーズに進行させることも十分に可能



わからないことがあるとストレスだったけど、流れを知るだけで、「できるかも」って思えてきますね



それは良かった。情報を持った上で、自分で選べるようになることが、ほんとうの意味での再スタートなんだ
あなたにとって、個人再生は正しい選択肢なのか。
それは、制度を知った今だからこそ、落ち着いて見極めることができます。
「どうすればいいか分からない」から、「こうしていこう」と思えるようになるまで、この記事が、あなたのその第一歩の“土台”になっていたら幸いです。