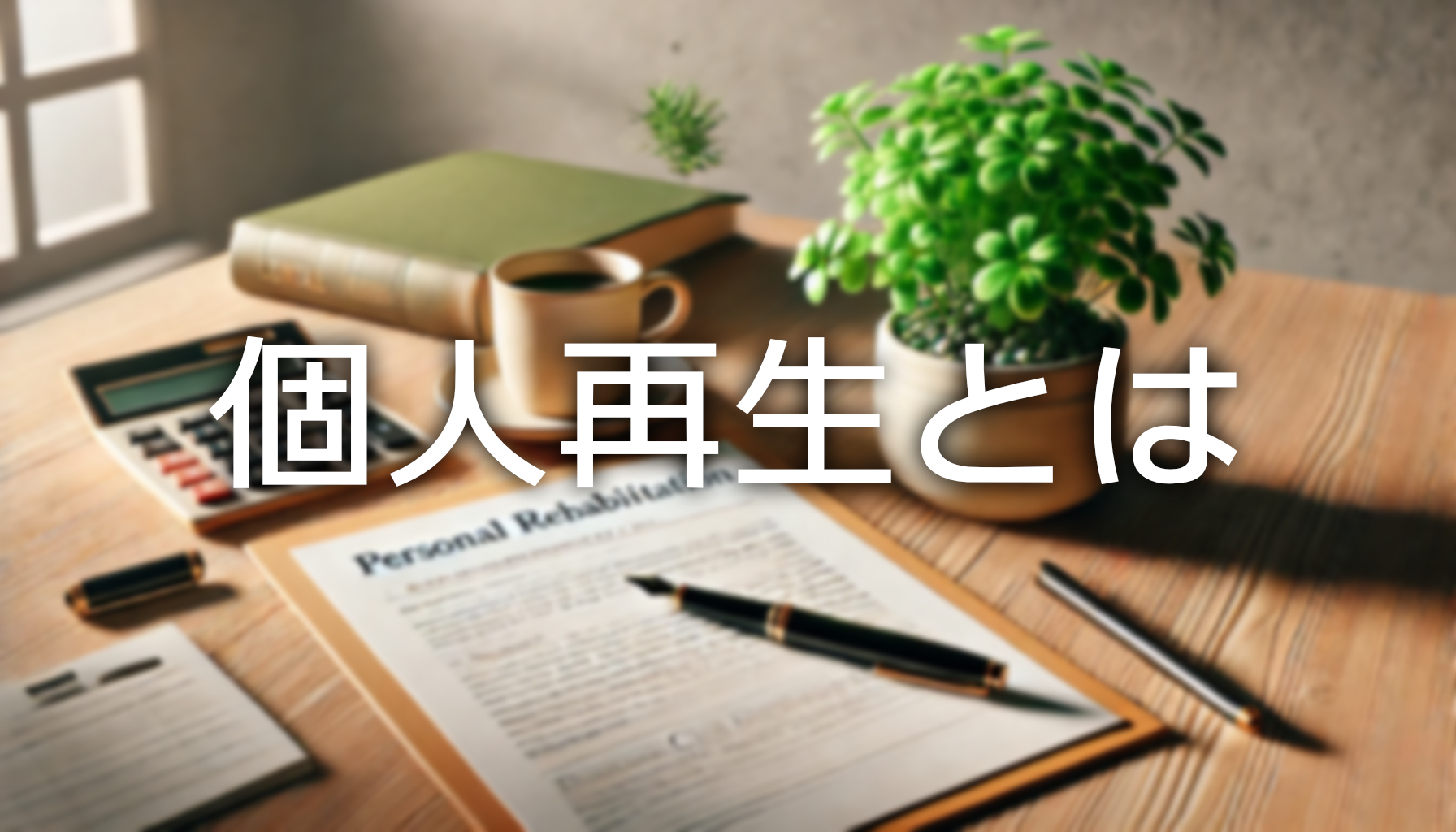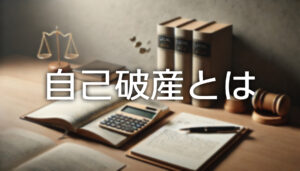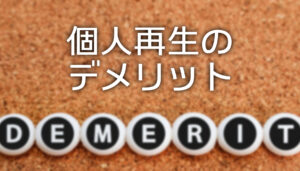「借金が減らせて、しかも家も守れる方法って……あるの?」
そんな都合のいい話、あるわけないと思っていませんか?
でも、実はあるんです。
それが、今回のテーマである 「個人再生」。
個人再生は、借金を大幅に減らすことができるうえに、自宅などの大切な資産を手放さずに済む可能性があるという、非常に現実的で力強い制度なんです。
とはいえ——
「裁判所って聞くだけでちょっと怖い…」
「自己破産とどう違うの?」
「住宅ローンがあっても使えるの?」
といった疑問が浮かぶのも当然。だからこそ本記事では、
「個人再生とは何か?」を0からわかりやすく解説しながら、手続きの流れ、費用、メリット・デメリットなどを丁寧にお伝えしていきます。
もちろん、2025年最新情報や実際の事例も紹介していますので、読めばきっと「そういうことだったのか!」と納得できるはずです。
 望月
望月ねぇ金崎さん、「個人再生」って自己破産とは違うんだよね?



うん、全然違うよ。「借金を大幅に減らしつつ、大事な家や車は守れる可能性がある」のが個人再生。特に住宅ローンがある人には強い味方なんだ。



そんな方法があったなんて、知らなかった…!



知ってるか知らないかで、未来は大きく変わるからね。よし、それじゃあまずは基本から説明しようか。
個人再生とは?借金を大幅に減らせる裁判所の制度
「借金が1/5になる?」
「しかも家も手放さずに?」
はい、それ、現実に起きている話なんです。
個人再生とは、簡単に言うと、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3〜5年で分割返済する制度です。
特筆すべきは、「自己破産のように財産をすべて失わずに済む可能性がある」という点。たとえば、住宅ローンがある人でも、条件次第で家を残したまま手続きできるというのが個人再生の大きな強みです。
では、もう少し詳しく見ていきましょう。
個人再生の基本的な仕組みと他制度との違い
個人再生は借金を約1/5にできる法的手続き
個人再生は、法律(民事再生法)に基づく手続きで、原則として借金総額を最大80%カット(=1/5に減額)できる仕組みです。しかも、残った借金は3〜5年の分割払いで返済していく計画を立て、それを裁判所に認めてもらえばOK。
たとえば、600万円の借金がある人なら、約120万円まで減額されることもあり、月々の返済額は3万円台まで下がることも。
ポイントは「裁判所が関与する」こと。
任意整理のような債権者との交渉型ではなく、法的拘束力があるので、債権者が反対しても手続きが進むケースもあります。
自己破産や任意整理とどう違う?特徴を簡単比較
一言で言うなら、個人再生は 「自己破産と任意整理の中間」のような存在です。
| 手続き | 借金の扱い | 資産の扱い | 裁判所の関与 | 信用情報への影響 |
|---|---|---|---|---|
| 自己破産 | 借金は全額免除 | 原則すべて処分 | 必要 | 約5〜10年 |
| 任意整理 | 利息カットが主 | 資産はそのまま | 不要 | 約3〜5年 |
| 個人再生 | 約1/5に減額 | 住宅ローン特例あり | 必要 | 約5〜10年 |



財産を守りつつ借金を減らしたい人には、まさに個人再生がうってつけです。
資産を守りながら生活を再建したい人に最適な理由
個人再生の最大の特徴は、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使えば、自宅を残したまま借金整理ができるという点です。
つまり…
✔「家は守りたい。でも借金も何とかしたい」
✔「自己破産はしたくない。けど任意整理じゃ減らしきれない」
そんな二律背反を抱える人にとって、最適なバランスを提供する制度が個人再生なんです。



個人再生って、裁判所が関わるから大ごとに感じるけど… 実際どうなの?



確かに手続きはちょっと複雑だけど、法律で借金を減らせるっていう強力な後押しがあるから、慎重にでも検討する価値はあるよ。



しかも家が残せる可能性があるって、かなり魅力的だね。



そう。とくに住宅ローンが残っている人にとっては、再スタートのチャンスになりうる手段なんだ。
個人再生のメリット|家や車を守りつつ借金を整理できる
借金を減らすだけじゃない、個人再生には「守れる」メリットがあるんです。
個人再生は、単に借金を減らせるだけの制度ではありません。むしろその真価は、「借金問題を解決しながら、大切なものを守れる」という点にあります。
たとえば、
「マイホームを手放したくない」
「車は仕事に必須」
「家族に迷惑をかけたくない」
そうした現実的な生活の中での願いに、かなり実践的に応えてくれる制度なのです。
個人再生で得られる具体的な利点とは
借金が大幅減額される|600万円→120万円の事例も
最大のメリット、それは 借金の大幅減額!
裁判所が認可した「再生計画(返済計画)」により、借金が最大80%減額される可能性があるのです。
具体例:
借金総額600万円 → 個人再生後 → 120万円(約1/5)に!
これを3年で返済すれば、月額約3万3,000円の返済で済む計算になります。
利息ではなく、元本(借金そのもの)をカットできる制度は個人再生だけ!
裁判所の手続きなので、法的効力がある。債権者の反対があっても手続きが進む可能性あり。
住宅ローン特例で自宅を手放さずに済む可能性あり
個人再生なら、自宅を守れるチャンスがあります。
その鍵となるのが、「住宅資金特別条項(住宅ローン特例)」。
この特例を使えば、
ということが可能です。
つまり、「家を守りたいから自己破産は無理」という人にとって、再建のチャンスを与えてくれる制度なのです。
ただし注意点もあり!
など、条件はあるので事前に確認が必要です。
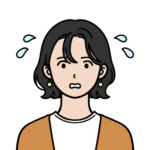
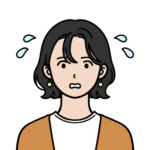
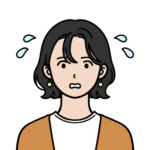
家って簡単には手放せないよね… 家族との思い出とかもあるし。



そうだね。個人再生の住宅ローン特則は、「住まいを守りながら借金を整理したい人」にとっては最後の砦になることもあるんだ。



ただ借金を減らすだけじゃなくて、守れるものもあるんだね。



その通り。個人再生は、人生をまるごと再生するための制度とも言えるよ。
保証人でなければ家族に影響が及ばない仕組み
もうひとつ、個人再生の大きなメリットは、
手続きをしても、原則として家族には影響が出ないという点です。
これはどういうことかというと…
個人再生は「自分の債務整理」なので、保証人になっていなければ、配偶者や親、子どもに迷惑がかかることはありません。
郵送物は「法律事務所名」などで届くことが多く、プライバシーに配慮されている。
官報に名前が載るものの、一般の人が閲覧する機会はほぼなし。
ただし保証人がいる場合、その人には請求がいく可能性があるため要注意!



「家族に絶対知られたくない」って人も多そうだよね…



そうだよね。個人再生は「自分の問題を自分で解決する制度」だから、保証人さえついていなければ、家族に知られる心配も少なくて済むよ。



それなら安心だね。打ち明けることも大事かもしれないけど、それ以前のプライバシーが守られるかってことも大切だし。



本当にその通り。誰にも知られずに借金問題を解決したい人にとっても、個人再生は現実的な選択肢になり得るんだ。
個人再生のデメリット|信用情報や手続きの注意点
どんな制度にもメリットがあれば、もちろんデメリットもあります。
個人再生も例外ではありません。
この記事では良い面だけでなく、「知っておかないと後悔するかもしれない」側面も正直にお伝えします。
なぜなら、きちんとリスクを理解した上で選ぶことが、最終的に自分を守る判断になるからです。
ここでは、個人再生を検討する前に知っておきたい4つの注意点を紹介します。
手続きのハードルと生活への影響
信用情報(いわゆるブラックリスト)に5〜10年登録される
個人再生をすると、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に「金融事故情報」が登録され、いわゆるブラックリスト状態になることは避けられません。
登録期間は 5〜10年。
この間は、以下のような影響が出ます。
- クレジットカードが作れない
- カーローン・住宅ローンが組めない
- スマホの分割払いも不可になる場合あり
ただし、ブラックリストは永遠ではありません!
期間を過ぎれば信用情報は回復し、クレジットカード作成や住宅ローン契約など通常の取引は可能になります。



えっ、ブラックリストって、スマホの分割払いにも影響するの?



うん、スマホの分割も「ローンの一種」だから、審査があるんだ。



それはちょっと不便だね。でも永遠じゃないっていうのは安心した。



「ブラック=人生終了」ではないから、そこは冷静に受け止めることが大切だね。
高額な資産は処分対象になる場合もある
基本的に個人再生は「資産を守りながら借金を減らす」制度ですが、すべての財産を無条件に残せるわけではありません。
特に注意したいのが、高額な資産(車や保険、株など)を持っている場合。
自宅は「住宅ローン特例」で守れるが、
✔ 自動車ローン中の車はローン会社に引き上げられる可能性あり。
✔ 時価が高い生命保険・株式などは、清算価値計算に影響。
申立から返済開始までに6〜7ヶ月かかる現実
個人再生のもう一つのネックが、手続きに時間がかかること。
弁護士への相談から実際の返済開始まで、
平均して 約6〜7ヶ月。
その間には:
- 書類の準備(収入・資産・借金内容)
- 「積立訓練」として、月々返済分を積み立て
- 再生計画案の作成と裁判所の審査
など、やることが多いんです。
けれど逆に言えば、その間に生活習慣を見直す準備期間にもできるのです。
時間はかかっても、制度としての安定性と信頼性はピカイチ。
官報に名前が載るが、ほとんど人に知られない
個人再生は裁判所を通す手続きなので、官報という政府の発行する公報に「名前・住所」が掲載されます。
「えっ!?全国にバレるの?」と心配になるかもしれませんが、ご安心を。
官報は一般人が見るものではありません。
インターネット検索に名前が出てくることはまずありません。
司法書士や金融機関など、一部専門機関がチェックするのみ。
「官報でバレる」は、ほぼ都市伝説レベル。



官報って、普通の人でも見れるの?



ちなみに、見たこととか探したこととかある?一応誰でも見れるけど、あえて見る人ってほとんどいないよ。国会図書館とかに行かないと紙では読めないしね。



じゃあ、「ネットで名前検索されたら出てくる」みたいなのは?



それはないね。少なくとも、官報が検索エンジンに引っかかることはないよ。



それならちょっと安心した!
個人再生の流れ|再生計画認可までのステップを徹底解説
「やってみたいけど、手続きがややこしそうで一歩踏み出せない…」
そんなあなたのために、個人再生の全体像を“道のり”として見える化します!
裁判所を通じて借金を減らす制度と聞くと、なんだかとっても複雑そうに思えますが、実はステップさえ押さえれば、そこまで難しくはありません。
このセクションでは、個人再生の全体の流れを「いつ」「誰が」「何をするか」に分けて徹底解説していきます!
弁護士への相談から返済開始までの全体像
まずは無料相談|借金額と収入を確認
まずやるべきことは、弁護士または司法書士への無料相談。
多くの事務所では、個人再生を含む債務整理に関して初回相談無料、または相談は何度でも無料などの対応で相談に乗ってくれます。
相談前に準備しておきたいもの:
・借金の総額・社数がわかる明細
・現在の収入状況(給与明細など)
・自宅や車などの資産情報
この段階で、「個人再生が本当に自分に適しているか?」を一緒に判断してもらうのが理想的です。



借金のことって、誰にも話せないし、相談に行くの怖そう…
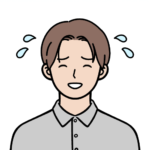
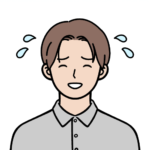
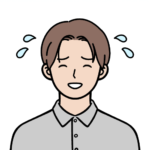
最初はみんなそうだよ。でも相手もプロだし、不安に思っていることを話すだけでも思った以上に気持ちがラクになる人が多いんだ。



そうだよね。無料なら、相談だけでもしたほうがいいのかな…



うん、それが再出発の第一歩だよ。相手も人間だし、話してみた相性なんかもあるから、気楽に複数事務所に相談してみるっていうのもありかも。
積立訓練で計画性をアピール
個人再生を裁判所に申し立てる前に、弁護士から「積立訓練」を提案されることがあります。
これは、返済可能性の証明として、毎月一定額を積み立ててみるという準備期間です。
積立期間:2~3ヶ月程度
積立金額:将来の返済予定額と同程度(月3~5万円が目安)
裁判所にも「この人はちゃんと返済できる人です」とアピールできる大事な材料になるため、このステップはとても重要です。
裁判所への申立〜認可の流れ
ここがいわゆる「個人再生手続き」の本番フェーズです。
弁護士がすべて代行してくれるので、負担は少なめですが、ざっくりと流れを知っておきましょう。
弁護士と相談しながら、借金・収入・資産などの情報をもとに必要書類を整えます。
上記の書類等を裁判所に提出します。弁護士が代行してくれます。
減額された借金をどのように返済するかを明記した「返済計画(再生計画)」を立てます。
再生委員は、裁判所が選任する中立的な専門家で、申立人の収入や支出、返済能力などを調査・報告する役割を担います。
通常は弁護士が務め、申立人との面談や家計のヒアリングを行い、計画の実現可能性を判断します。
再生計画案が債権者に送られ、同意・不同意などの意見が裁判所に提出されます(小規模再生では過半数の同意が必要)。
債権者の反対が多すぎると、小規模個人再生では計画が通らない場合も(※給与所得者等再生ならその制約なし)
再生計画に問題がなければ、裁判所が「再生計画認可決定」を出し、手続きが正式にスタートします。
再生計画が認可されれば、減額された借金のみを返済すればOK!
期間の目安は、申し立てから認可までは4〜6ヶ月程度です。
裁判所による認可後は3〜5年で完済を目指す
再生計画が裁判所に認められたら、晴れて新しい生活のスタートです!このあとは、計画通りに3〜5年かけてコツコツ返済していくだけです。
返済中の注意点:
返済が1回でも遅れると「計画取り消し」になる可能性あり。
急な収入減などが起きたら、すぐに弁護士に相談を。



計画的な生活を支える「再生」の3年〜5年は、「借金を返す時間」であると同時に、「お金の習慣を整える期間」でもあります。



でも、6ヶ月かけて手続きしてさらに3〜5年で返済かぁ… 長いなぁ…



確かに簡単ではない。でもね、その時間を「人生を立て直すプロセス」だと捉えると、すごく価値のある時間になるんだ。



なるほど… 短期決着じゃなくて、将来を見据えた制度ってことか。



うん、個人再生って、借金を減らすための制度というより、「未来を再構築する制度」なんだ。
個人再生の条件|利用できる人・できない人の違いとは?
「個人再生って良さそうだけど……誰でも使えるの?」
そう思ったあなた、大正解です。
いくら魅力的な制度でも、すべての人が無条件で利用できるわけではありません。個人再生には、法律で定められた明確な「利用条件」があります。
ここでは「あなたが個人再生を使えるかどうか」を自己チェックできるように、具体的な条件をわかりやすく解説していきます!
申立に必要な条件とチェックポイント
借金総額500万円以下(住宅ローンは除外)
まずチェックすべきなのは、借金の総額です。
個人再生には2種類ありますが、一般的な「小規模個人再生」の場合、住宅ローンを除いた借金が500万円以下であることが原則条件です。
カウントされる借金の例:
クレジットカード・カードローン
消費者金融
携帯電話の割賦残債
カウントされない借金:
住宅ローン(住宅資金特別条項が適用されるため
※借金が500万円を超える場合でも、条件を満たせば「給与所得者等再生」という制度を利用できる可能性があります。
継続的な安定収入があるかどうか
個人再生の大前提は、「減額された借金を、きちんと返していけること」。
つまり、将来的に安定した収入が見込めることが条件になります。
安定収入の目安:
月収10万円以上が継続してある。
雇用形態は正社員でなくてもOK(アルバイト・パート・年金生活者も対象)。
主婦でも、配偶者の収入で生活が安定していれば認められることも。
「副業収入」「扶養的な仕送り」なども評価対象になることがあります。
「収入の多さ」よりも、「安定しているか」が問われる制度です。



えっ、主婦や年金生活者でもできる可能性があるの?



あるよ。重要なのは、「今後の返済を安定的に続けられる見込みがあるかどうか」なんだ。



じゃあ、非正規でも諦めなくていいんだね… ちょっと希望が持てる。



うん、「生活の実態」を重視してくれるのが個人再生の特徴でもあるんだ。
小規模再生では債権者の多数決に注意
個人再生の種類のうち、一般的なのは「小規模個人再生」ですが、この方式では、債権者の同意が必要な「多数決ルール」が存在します。
条件はこの2つ:
債権者の過半数(人数ベース)が同意していること。
債権額の過半数(総額ベース)が同意していること。
どちらかの条件が満たされないと、計画が認可されないリスクもあります。
「給与所得者等再生」を選べば、債権者の同意は不要になりますが、収入の変動が少ないことなど、さらに厳しい条件をクリアする必要があります。
住宅ローン特例を使うための追加条件
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使いたい場合には、以下の条件が追加されます。
自宅が「自己の居住用不動産」であること(別荘や投資物件はNG)。
住宅ローン以外に抵当権が設定されていないこと。
住宅ローンを滞納していない or 滞納分を分割で返済可能であること。
住宅ローンを返しながら、その他の借金だけを減額するという設計なので、「住宅を維持できる返済能力」が必要とされます。



家を残せるって聞いたけど、それなりに条件があるんだね。



うん、でも条件を満たせば、家を守りながら借金を再スタートできるっていうのはかなり大きい。



たしかに、家族がいる人にとっては、それだけで選ぶ価値がある制度かも。



だからこそ、「自分が条件に合っているか」を早めに確認するのがポイントなんだ。
個人再生の費用は?分割払い・法テラスの活用法も紹介
「手続きにお金がかかるって聞いたけど、いくらくらい?」
「そもそもお金がないから個人再生したいのに…」
そう思った方、ご安心ください。
個人再生の費用は高額に感じるかもしれませんが、実は「工夫次第で無理なく支払える」制度になっています。
このセクションでは、実際にかかる費用の内訳、支払い方法、そして法テラスを活用する方法まで、徹底的に解説していきます!
手続きにかかる費用の内訳と相場
弁護士・司法書士費用の相場は30〜55万円
個人再生の費用の中心は、弁護士(または司法書士)への報酬です。
一般的な相場(※全国平均)
- 着手金:20万円〜30万円
- 報酬金:10万円〜20万円
- 再生委員対応費用:5万円〜10万円(裁判所が選任する場合)
多くの事務所では、合計30〜55万円程度に収まることがほとんどです。
また、費用は依頼する事務所によって異なるため、必ず事前に見積もりを取りましょう!
裁判所への納付金は約5.5万円
手続きの中では、裁判所に対しても一定の費用を支払う必要があります。
内容と金額(目安)
- 収入印紙・郵券・予納金などで 約5.5万円
- 再生委員が選任される場合は、さらに5〜15万円程度上乗せされることも
費用総額のシミュレーション(住宅あり/なし)
下記は、一般的なケースにおける総費用の目安です:
| ケース | 弁護士費用 | 裁判所費用 | 合計費用 |
|---|---|---|---|
| 住宅なし | 約30万円 | 約5.5万円 | 約35.5万円 |
| 住宅あり(再生委員付き) | 約40万円 | 約10万円 | 約50万円前後 |



もちろん、依頼する法律事務所によっては、もっと安く済む場合や分割払いが可能なところも多いです。
分割払い・法テラスを利用する方法
お金に余裕がない方も、諦めるのは早すぎます。
分割払い対応の事務所や、「法テラス」という制度を使えば、初期費用ゼロで進めることも可能です。
分割払いに対応している事務所も多い!
- 「着手金0円+毎月1〜3万円の分割払い」など
- 「和解成立後に支払い開始」という柔軟な方式も増えています
法テラス(日本司法支援センター)を活用するには?
- 一定の収入基準以下であれば、弁護士費用の立替制度が利用可能
- 月々5,000〜1万円程度の分割返済でOK
- 相談料も無料(初回)
利用条件の一例(2025年現在)
- 単身者:月収22万円以下+資産60万円未満
- 2人世帯:月収25万円以下+資産180万円未満



50万円近くかかるって聞くと、ちょっとビビる…
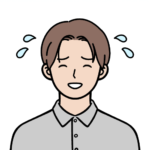
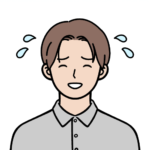
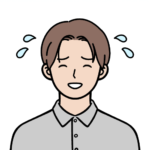
確かに金額だけ見ると高く感じるけど、分割できるし、利息のカットや借金総額の減額効果を考えれば、実質的には「元が取れる」制度でもあるんだ。



なるほど… 法テラスも使えるなら、初期費用なしで進められるかも?



そう。だから「費用が不安」って理由で諦めるのはもったいないよ!
個人再生を検討中の方へ|安心して一歩を踏み出すために
「個人再生の内容は理解できたけど、じゃあ実際にどう動けばいいの?」
「何から始めたらいいのか分からない…」
そんなあなたに向けて、“今すぐできる3つの行動プラン”をご提案します。
不安を抱えたまま立ち止まるより、小さな一歩を踏み出すことのほうが、確実に人生を前に進めてくれます。
相談・準備・心構えの3つのステップに分けて、次にやるべきことを明確にしていきましょう!
行動前に知っておきたい3つのポイント
まずは無料相談で、手続き全体の流れを把握
最初にやるべきこと。それは、無料の法律相談を受けること、です。
「自分は本当に個人再生を使えるのか?」
「自己破産や任意整理のほうが向いているんじゃないか?」
そうした疑問も含めて、専門家に相談することでクリアになります。
無料相談でわかること:
- どの債務整理が自分に合っているか
- 実際の手続きスケジュール
- 予想される費用とその支払い方法
- 成功率の目安や注意点
- 借金解決までの道のりの具体性がぐっと高まる



まずは気になった事務所に1回だけ、相談してみると視界がパッと開けるはずです!
必要書類や証明書は早めに準備しておく
個人再生の手続きでは、裁判所への提出書類が多く発生します。
事前に準備しておくと、相談後〜申立までの手続きがスムーズになります。
📎 よく求められる書類:
- 直近2〜3ヶ月分の給与明細
- 源泉徴収票または確定申告書
- 借金の明細(クレジットカード明細、ローン契約書など)
- 家計簿または生活費の内訳(メモでも可)
- 資産の資料(保険証券、不動産の評価証明書など)



書類が手元にあればあるほど、相談時の精度が高まり、提案されるプランも現実的なものになります。
不安な気持ちは、専門家のサポートで解消できる
手続きの流れ、裁判所とのやりとり、債権者との調整、返済計画の作成…。
一人でやろうとしたら、どれも不安になりますよね。
でもご安心を。
個人再生は、プロと一緒に進める制度です。
弁護士や司法書士は、あなたの味方です。
彼らは何十、何百というケースを扱ってきた経験者。
だからこそ、あなたの状況に合った最適な方法を提示してくれます。
「たった一人で、制度のことをすべて理解する必要はない」
この言葉を、ぜひ覚えておいてください。



もし私だったら…相談に行くまでが一番ハードル高そう。
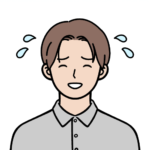
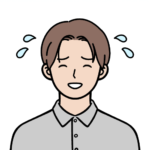
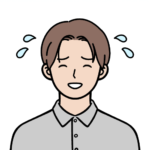
分かるよ。でも“知らないこと”って、実は「怖い」よりも「損してる」ことが多いんだよね。



相談って、迷ってる段階でもいいのかな?



もちろん!むしろ「迷ってる段階」こそ相談してほしいんだ。行動のタイミングを逃すと、解決できたはずの問題が手遅れになることがあるから。



よし…何かあったら、まず相談してみようかな。



うん、まずは最初の一歩だけ、踏み出してみよう
個人再生は「借金整理」というより「人生の再構築」
個人再生とは、単なる「お金の手続き」ではありません。
借金という足かせを減らし、守りたいものを守りながら、自分の未来を立て直すための制度です。
この記事を最後まで読んでくださったあなたは、すでに一歩目を踏み出している状態です。
次の一歩は、無料相談という小さなアクション。
そこから、人生の再構築が始まります。
どうか勇気をもって、あなたの未来のために動き出してください。
応援しています!